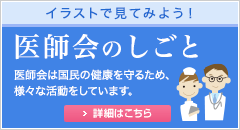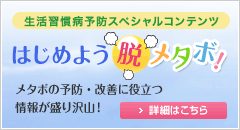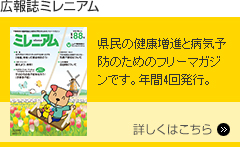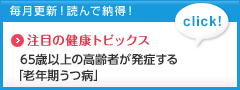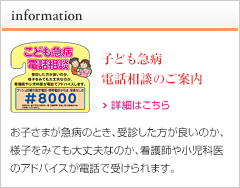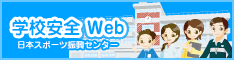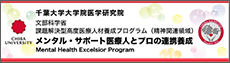古い情報のページを削除いたしました。
クリックされた記事は、公開当時の情報に基づいており、
今日の知見では誤解を招く恐れがありますので、現在非公開にしております。
大変恐れ入りますが、新たな記事の公開をお待ちください。
公益社団法人 千葉県医師会 CHIBA MEDICAL ASSOCIATION みんなで高めるいのちの価値 ~健康と福祉のかなめ~
〒260-0026千葉県千葉市中央区千葉港4-1
TEL 043-242-4271
FAX 043-246-3142